
《対談・前編》武井 浩三 氏 × 石原 紳伍
武井 浩三(社会活動家・社会システムデザイナー)
1983年、横浜生まれ。
2007年にダイヤモンドメディア株式会社を創業。会社設立時より経営の透明性をシステム化。独自の「管理しないマネジメント思想」は次世代型企業として注目を集める。
2017年には「ホワイト企業大賞」を受賞。
ティール組織・ホラクラシー経営等、自律分散型経営の日本における第一人者としてメディアへの寄稿・講演・組織支援などを行う。
2018年にはこれらの経営を「自然(じねん)経営」と称して一般社団法人自然経営研究会を設立、代表理事を務める。組織論に留まらず、自律分散・持続可能・循環経済をキーワードに、社会システムや貨幣経済以外の経済圏など、社会の新しい在り方を実現するための研究・活動を多数行なっている。
ここ数年話題になっている、フラットな組織形態を表す「ホラクラシー」や社員ひとりひとりが自発的に行動する「ティール組織」の第一人者である武井浩三氏さんが、2020年、メゾンカカオのアンバサダーに就任した。
新型コロナウイルスによる世界的パンデミックによって、日本では硬直化した組織や制度が露わになり、従来の働き方、生き方に対する価値観も揺らいでいる。世の中が急速に変化しつつあるなかで、企業、そして個人にはなにが求められるのか?
現在も多彩な活動を通して社会を見つめている武井さんと、「世界的な100年ブランド」を目指すメゾンカカオの石原紳伍社長が、「これから」を語り尽くした。

「資本主義の次の社会」を見据えて
石原:武井さんは、フラットな組織形態を表す「ホラクラシー」や社員ひとりひとりが自発的に行動する「ティール組織」のような経営を実践した先駆者なんですが、その取り組みが本当にユニークなんですよね。
武井:僕は2007年に不動産向けITサービスを提供するダイヤモンドメディアという会社を立ち上げました。その時に「自分の給料は自分で決める」「肩書きは自分で決める」「財務情報は全部オープン」「働く時間、場所、休みは自分で決める」「代表、役員は選挙と合議で決める」などの取り組みを始めたんです。
それが今、「ホラクラシー経営」「ティール組織」と言われる経営思想です。当時はまだ珍しかったので、面白いことをしている経営者として注目されるようになって。
石原:2017年には、ホワイト企業大賞を受賞していますよね。武井さんの経営論に感銘を受けたこともあって、今年からメゾンカカオのアンバサダーに就いてもらったんですが、最近はほかにどんな活動をしていますか?
武井:社員も35人くらいに増えて、社会状況も変わっていくなかで、僕がやりたいことが会社の外にどんどんはみ出していったので、去年の9月に会社を後任に譲りました。
今は株式会社の経営だけでなく非営利組織や地域の活動などもしているんですが、シンプルにいうと「資本主義の次の社会を作る活動」をしていて、社会活動家と名乗っています。例えば、「自然のように変化し続ける経営」を目指す自然(じねん)経営研究会という社団法人の代表理事のひとりで、ここはメンバーが約1700人います。ほかにも新しい組織の在り方を広める活動をしたり、これまでにない通貨を作る会社の経営に携わったり。
飽和した日本のマーケット
石原:活動の幅が広いですよね。「資本主義の次の社会」には、僕も興味があります。
武井:シンプルにいうと、お金でお金を増やす、それが資本主義ですよね。そうやってお金でお金を増やして短期的な利益を追うとなにが起こるかというと、環境と人権が毀損されるんです。上場企業の社員も、経営者も、会って話してみるといい人なんだけど、株式市場というマーケットから、毎年増収増益しろ!ってプレッシャーがかかるから、責任感のある人ほど頑張ってどうにかしようとする。
石原:なるほど、確かにそうですね。
武井:でも、日本は2010年から人口が減っているんです。GDPは人口とほぼ正比例するから、人口が減るということはGDPが下がって然るべきだし、そもそもITが発達すると中間流通や無駄が省かれるので、GDPは下がるんですよ。それなのに、国はGDPを増やそうとしているし、経営者は必至で増収増益を目指している。でも、もう日本のマーケットは飽和していて限界にきてるから、無理な手を打っておかしなこと起きるんですよ。問題を起こす上場企業がたくさんあるでしょう。
石原:そうですね。僕もひとりの経営者として、考えさせられます。僕自身、日本の経済成長には限界を感じていて、今後の日本の未来を見据えた時になにが大切なのかを考えた時にたどり着いた答えが、「文化創造」でした。
文化を育むことで、経済とは違うところで日本はまだまだ豊かになれると思ったんです。
初めてコロンビアに行った時、生活者と生産者の近さやチョコレートが日常に溶け込んで、笑顔が生まれる風景に魅せられて、チョコレートを通して、新しい日本の文化を創造したいという思いで創業しました。

人間が残したいと願い、残ってきたものが文化
武井:石原さんの「メゾンカカオで文化を作りたい」という想いに僕はすごく共感していて、だからなにかお手伝いできればと、アンバサダーに就任したんです。
文化といえば、最近、西暦578年創業で、世界最古の会社である大阪の金剛組の見学にいったんですけど、しびれましたよ。この会社は飛鳥時代に聖徳太子が百済から連れて来た金剛さんという人が創業した会社で、今も神社・仏閣を作っているんですけどね。
宮大工の人たちに仕事のモチベーションってなんですかって聞いたら、その話がめちゃくちゃ面白い。そもそも宮大工の仕事ってPDCAが300年ぐらいのスパンでまわっていて、自分の仕事を評価されるのが300年後なんですよ。
石原:300年!
武井:そう。遠い子孫に「いい仕事したな」と言われたいというのが職人たちのモチベーションなんです。ほとんどの企業は売り上げや利益を優先してきたけど、金剛組がやってきたことは、お金とは別次元の話ですよね。
もちろん、会社としてお金を稼がないと存続できないのが資本主義なんだけど、金剛組の歴史を振り返ると、経営が厳しくなった時に寄付が集まったり、職人さんたちが無報酬で働いたりしてきたそうです。数年前も経営破綻しかけたんだけど、高松建設が「金剛組を潰したら、大阪の恥や」と救済した。僕は「人間が残したいと願い、残ってきたものが文化」だと思っているから、これこそ文化だ、素敵な話だなと感動したんですよ。

「文化を紡ぐ」ために必要なこと
石原:前回、山口周さんがいらっしゃった時(※)も、日本ではもうお経済発展、経済成長は難しくなっていて、我々は「高原」にいると話していました。高原社会のなかで我々がどういう役割を担っていくかというところで、これからのメゾンカカオはどう在るべきだと思いますか?
武井:まず、ここに集まっているスタッフのみなさんだけじゃ、文化は作れないと思うんです。お客さんとか、鎌倉の関係者、ステークホルダー、自分たちの家族とか、みんなでブランドを育んでいく必要性があって。金剛組もそうですけど、文化って時間軸のなかに存在するもので、みんなで紡いでいかないといけない。紡いでいくという行為は、共同作業とか対話とか、一緒になにかする、一緒の時間を共有することによって育まれます。
石原:なるほど。わかります。
武井:だから、これが正解だからこの通りにやってね、だと文化は育まれなくて。これからのチーム作り、組織作りもそうなんですけど、ひとりひとりの想いや意見を丁寧に掬い上げ、重ね合わせていく、それをずっとやっていくことで文化になっていくというのが僕の持論です。
石原:その切り口でいうと、うちは大人の本気の運動会をしたり、バーベキューをしたり、交流の機会を意識的に作っています。そうすることでメンバーの関係構築ができるから、いつも手伝ってくれるあの人のためなら、私もこれをやってあげようという感じで、いい意味で業務が業務でなくなっていく雰囲気がありますね。
もうひとつ、当事者意識を育むために、マニュアルをあまり作らないようにしています。我々は他業種からきているメンバーがほとんどで、「やったことない」「できない」からスタートなんですね。だから、どうできるかをみんなで考えようというスタンスでやってきました。
武井:まさに、そういう試みが「文化を紡ぐ」ために必要なことだと思います。
石原:小手先のテクニックではなくて、「みんなでブランドを育んでいく」っていいですよね。僕にとって、メゾンカカオは「家族」なんです。社員はもちろん、ファンになってくださったお客様やそのコミュニティの方々に一緒に育ててもらっているという感覚が強いんです。今後も、お客様を含む「家族」としてブランドを創っていきたいと思っています。

武井さんが「文化」の例に挙げた金剛組の存在は、象徴的だ。
資本主義のもと、企業が目先の売り上げや利益を追求するのは当前だと思われてきたが、1442年も存続し、数々の経営危機を乗り越えてきた金剛組は、「自分たちのため」ではなく、社会や未来のために仕事をしてきた。そして、その価値観を今も守り続けている。
資本主義による経済の拡大が限界に達しているとするなら、そのなかで持続可能な社会を目指すのなら、金剛組の在り方や取り組みが、ヒントになるのではないだろうか?
存在自体が「文化」と言われる世界最古の企業が日本にある。それは、大きな財産だ。「100年続くブランド」を目指すメゾンカカオは、金剛組のような存在になることができるだろうか? その挑戦は、まだ始まったばかりだ。
—後編に続く
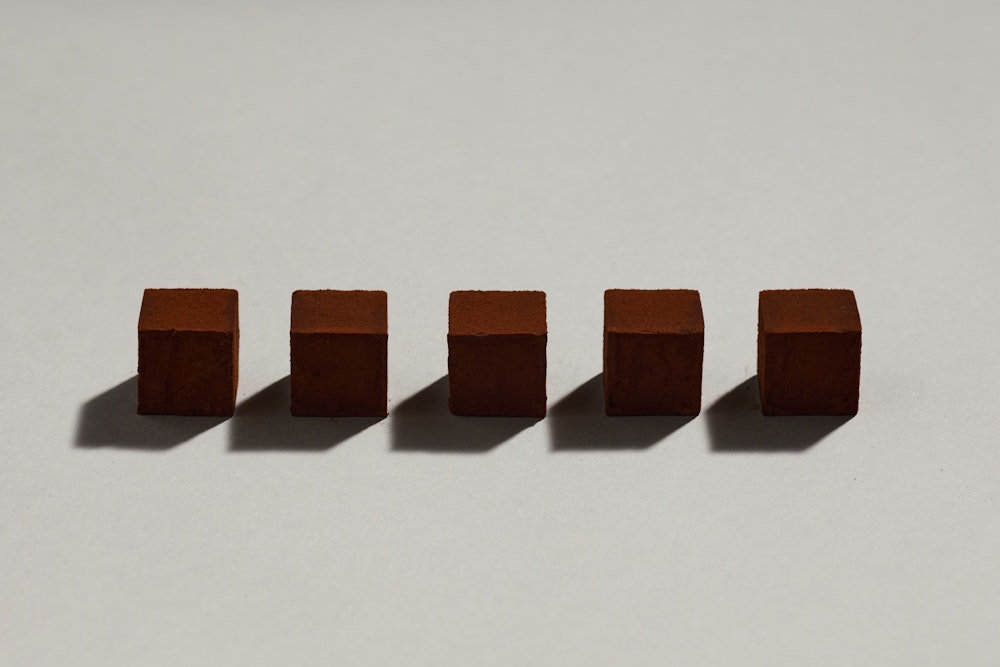
Written by
川内 イオ(Io Kawauchi)
1979年、千葉生まれ。ジャンルを問わず「規格外の稀な人」を追う稀人ハンター。2002年、新卒で広告代理店に就職するも9ヶ月で退職し、03年よりフリーライターに。06年、バルセロナに移住し、主にサッカーを取材。10年に帰国後、2誌の編集部を経て再びフリーランスに。現在は稀人ハンターとして複数メディアに寄稿するほか、イベントの企画やコーディネート、モデレーターなど幅広く活動する。2019年秋に発売した『農業新時代 ネクストファーマーズの挑戦』(文春新書)は4刷り18000部。今年10月、新著『1キロ100万円の塩をつくる 常識を超えて「おいしい」を生み出す10人』(ポプラ社)発売。




